


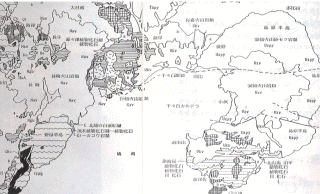
|
*東長崎
埋め立て地の崖

*断層 下からマグマが上がってきて,そのときの力でずれて断層になっている。
*地層の上下をみる。泥→砂へと変化=海が深くなったことがわかる。
|
侍石層有孔虫 大きい物で1~2mm 平板で巻いている |
細長い
|
|
 |
佐田岳(トロイデ)
角閃石安山岩を採石している。
柱状節理がきれいだったが、最近ははっきり見えなくなった。
飯盛岳、八天岳、普賢岳
= 行仙岳火山岩類という
|
 |
*江の浦
海岸のれき層の上に下釜層(カキ,二枚貝,クルミ,幹などの化石を含む)がある。これより下は角閃石安山岩があるが、不整合の関係です。
不整合面の上にはれき層ができるので探してみよう。
|
 |
移動の途中-千々石断層
この付近には、巨大な輝石の入った安山岩のれきがみられる。畑の石垣にもたくさん見られるのですが,壊したらいけません。
|
||
有喜海岸  |
輝石の結晶
赤い岩石は、酸化している、青っぽいのは還元状態 。見かけが違っているが、輝石はほとんど均等に入っている。 先に輝石の結晶が生成されたことがわかる。
 |
輝石安山岩の顕微鏡写真
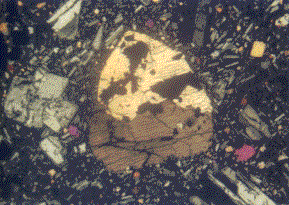 |
|
唐比ラグーンと泥炭地 島原半島をほぼ東西に横断(図A・・・B・・C・・・D・・・E・・・)して火山性の大規模な活断層=千々石断層(ちぢわ断層)がのびている。写真からわかるように、千々石断層は、雲仙火山のすそ野を切っているので、そんなに古いものではないと推定される。手前の唐比ラグーン(現在は水田になっている)には、多量のデイ炭=ピート層がうもれ、以前に弥生時代の丸木船などが発掘された。ラグーンの右はしE地点付近に唐比温泉がわきだしている。
**体験--泥炭地でジャンプしてみよう!
泥炭を採集しよう
|
 |
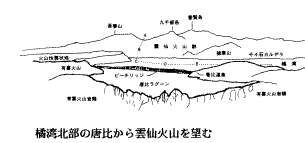 |
|
千々石断層- 展望所より |
|||
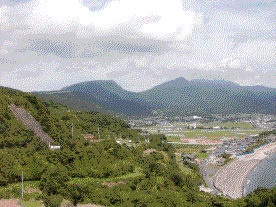 |
←中央の吾妻岳と九千部岳の間(田代原)へと断層が続く。手前が、断層崖のものである。断層崖に展望所があり,崖に沿って国道が造られている。100mの崖であるが、断層の最大落差は300mあり南側(橘湾)に落ちている。風化、浸食により、地形はしだいに崩れていっている。
|
千々石より断層崖を望む→ |  |
 |
断層崖の下から見たところ
←雲仙火山の泥流が、何度も堆積して私たちの立っているこの厚い地層ができている。
|
||
|
島原半島
島原半島は,中央部に,雲仙火山(雲仙岳)が,東西20km,南北25kmの広大な地域を占めています。雲仙火山は遠くから見るとひとつの山のように見えますが,実際は,普賢岳,国見岳,妙見岳,九千部岳などの溶岩ドームによって形成される複成火山です。
雲仙火山の噴火活動は,およそ50万年前に始まったと考えられています。
九千部岳や高岳などは侵食が進んだ古期の火山体で,50万年前から10数万年前のあいだに噴火してできたと考えられています。その後,およそ10万年前ころから,野岳,妙見岳,普賢岳の順に形成されました。島原半島の南端地域では,初期の雲仙火山の火山砕屑物が堆積した竜石層や,それ以前に形成された,島原半島の基盤である口之津層群などの古い地層を見ることができます。 雲仙火山では,東西方向に走る大きな断層によって中央部が落ち込んで,「雲仙地溝」が形成されています。北側の千々石断層と南側の深江断層,布津断層,金浜断層がおもなもので,そのあいだにも多くの断層があります。
|
約160万年前
島原半島南部に見られるこのころの地層(口之津層群)からは,シカやカメ,ウニなどの化石が産出しています。これらは中国大陸の第四紀更新世(洪積世,約160万年-1万年前)早期のものに近い種類のもので,かつて,この地域が大陸と陸続きだったことをうかがわせています。
|
約50万年前-35万年前
火山活動か始まり,火山砕屑物が口之津層群の上に堆積しました。過去の雲仙火山の噴火も,今回の噴火のように火砕流や土石流をくり返したと考えられます。
|
現在
東西方向に走る断層によって「雲仙地溝」か形成されています。千々石断層は,南落ちの正断層で,落差は最大のところで約300mほどあります。深江断層,布津断層,金浜断層は,いずれも北落ちの正断層で,深江断層は50mほどの落差をもっています。
|
|
地殻の深いところにあるマグマは 一般に水を含んでいます。火山噴火にともなって,マグマが火口近くまで上昇してくると,
圧力は下がり,水が溶けることのできる度合い(溶解度)は急激に減少し,溶けていた水分は水蒸気として分離し,マグマに気 泡が出来ます。 下の図は火砕流が起きる様子です。火砕流発生のしくみ(1991年6月8日20時06分の場合)(工業技術院地責調査所『雲仙火山地質図』1995年より)
|
|||
| ①溶岩ドーム下の山の斜面がくずれることにより溶岩ドームがくずれる。 | ②溶岩に含まれるガスが爆発してくずれる。 | ③壊れた溶岩と山の土砂が一体となって斜面を流れ下る。溶岩がくだけるたびに高温のガスが発生する。 | |
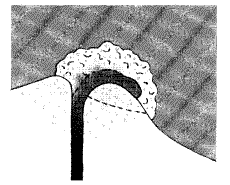 |
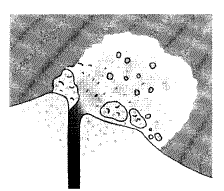 |
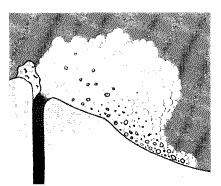 |
|