
| 地質時代 | 高島炭田 |
崎戸・松島炭田 |
|||
第 三 紀 |
漸 新 世 |
西彼杵層群 | 日切層 ⑪ | ||
| 塩田層 | |||||
| 百合岳層 | |||||
| 徳万層 | |||||
| 伊王島層群 |
大明寺層 | 間瀬層 ⑩ | |||
| 船津層 |
松島層群 | 崎戸層 石炭 | |||
| 中戸層 |
|||||
始 新 世 |
馬込層 | ||||
| 沖の島層 | |||||
| 高島層群 | 端島層 石炭 |
||||
| 二子島層 石炭 |
寺島層 |
||||
| 赤崎層群 | 香焼層 |
赤崎層 |
|||
|
①三重中
三重中の下の海岸に見られる褶曲した結晶片岩です。
黒色片岩は、砂~泥質のたい積物が、緑色片岩は、火山性の火山灰がもとになっているといわれている。
これらが、古生代~中生代初期の海底に、非常に厚くたい積し、中生代の白亜紀後期(6000万~9000万年前)の造山活動で、もとのたい積岩中の鉱物が再結晶する際、一定方向に並んでうすくはげやすい結晶片岩になった。また、高温高圧下では、ヒスイもできた。海岸のヒスイは県の天然記念物になっているので採集できない。標本が科学館においてあるので、見学してください。
|
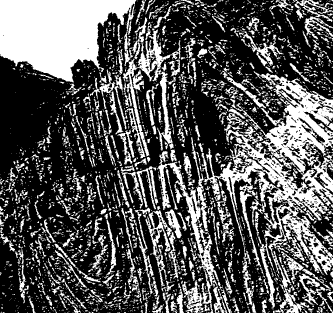 |
|
②琴海町西海
ア ン ザ ン 岩
カクセン石アンザン岩
アンザン岩は,南アメリカのアンデス山脈に広く分布していることから,英語でAndesite = アンデサイト と呼ばれ,日本語では安山岩=アンザンガンと訳されました。ふつうは,灰色か黒っぽい灰色をしていて,日本の火山には一番多い岩石です。造岩鉱物はふつう,白色のチョウ石と,黒または暗緑色のキ石や,カクセン石ですが,クロウンモや,わずかにセキエイやカンラン石を含むこともあります。 これらの有色鉱物により,アンザン岩を,シソキ石アンザン宕・フツウキ石アンザン岩・複キ石アンザン岩・カクセン石アンザン岩・クロウンモアンザン岩などに分けることがあります。 またアンザン岩は火山岩のなかまなので,石基とはん晶があり,これを「はんじょう組織」といいます。
西海から三重方向へ少し入った所に,採石揚があり,道路からもみごとな柱状節理を見ることができる。この節理は,マグマが冷えて固まるときに収縮し規則正しい割れめができるためで,板状のものを板状節理といいます。
この採石揚の岩石は,白っぱい灰色で,カクセン石のはん晶を見ることができます。カンラン石やキ石も含むので,カンラン・キ石・カクセン石アンザン岩と呼ぶこともあります。
|
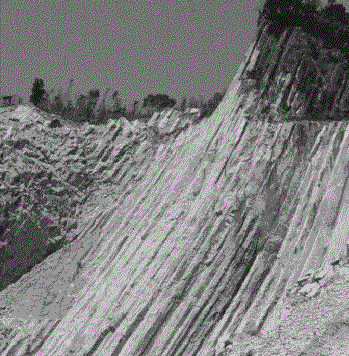 |
||
|
③琴海町戸根
西彼杵変成岩中に、マンガン鉱床が形成されている。この付近には、閉山した鉱山あとが残っている。黒い炭のような固まりは、二酸化マンガンで、みなさんは過酸化水素水の触媒として、酸素の発生で使ったことがあると思います。また、全国的にも珍しい、ブラウン鉱の結晶がある。絹雲母片岩中に、赤い紅簾石を含み、鉱床から遠ざかると藍色の藍閃石を含む。マンガンは、三重、村松、戸根、長浦などで採掘されていた。
|
|||
|
④琴海町長浦
⑤西彼町バイオパーク付近
リュウモン岩
マグマが地表に噴出して,急速に冷えかたまってできる火山岩の中で,SiO2(二酸化ケイ素)の量が66%以上のものを,リュウモン岩と呼ぶ。見かけや色はさまざまであるが,一般的にその色は白色で表面には溶岩として流れたときの跡であるしま模様(流理)が観察される。斑晶としてはクロウンモ.カクセン石.セキエイ.チョウ石 などが含まれる。この他にマグマが急激に冷却して,ガラスのような状態で固化したものがあり,その色からコクヨウ岩と呼んでいます。
写真は西彼杵郡亀岳付近に見られるリュウモン岩で,流理の様子がよくわかる。亀岳周辺では,最下部にリュウモン岩質の凝灰岩をはさみ,その上位にリュウモン岩質ギョウカイカクレキ岩・リュウモン岩質溶岩がかさなる。このことから,この火山活動は,最初は火山灰や火山レキを噴き上げる爆発的な活動を行ない,その後リュウモン岩溶岩を流す静かな活動に移ったことがわかる。
|
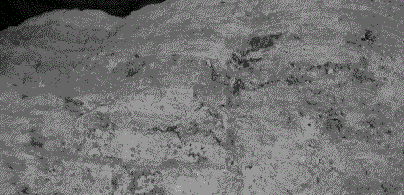 |
|
⑨多以良~柳
板の浦トンネルから直線谷をつくり国道沿いに断層が走っている。
呼子ノ瀬戸断層は,西彼杵半島の西海岸を南北に走る大断層で,南串島のすぐ西側を通り,柳・多以良川・梨ノ木・上越・東浜にぬけるものです。その一部がここで見られ,多以良断層と呼ばれています。国道の手前側が西彼杵変成岩の黒色片岩、一番高い部分に西彼杵層群の間瀬層の砂岩が見えます。その間は草が生えて見にくいですが断層破砕帯になっています。
|
 |
||
|
⑩西海町七ツ釜
七釜しょう乳洞
西彼杵半島北部の西海町西海岸に分布する地層は,西彼杵層群とよばれ・西彼杵変成岩類を不整合におおって発達しています。おもに,砂岩~レキ岩・砂岩~デイ岩の互層からなる部分が多く、その中に石灰ソウ類や二枚貝類の化石が大量にふくまれています。
石灰ソウ類はきれいな海水にしか生活できないといわれていますが,七釜の川内川流域の地層(間瀬層)には、とくにこの石灰ソウ類の化石が多くふくまれているため,地層全体が石灰岩に近く,いくつかのしょう乳洞が発達しています。また,中浦付近には,ドリーネ(すりばち穴)やポノール(すいこみ穴)もみられ準カルスト地形を形成しています。
七釜しょう乳洞付近の地層は・天然記念物に指定されていますので持ち帰ってはいけません。
採集したい場合は,中浦西海岸の転石を採集するようにしてください.
*七釜(ななつがま)…おもいろい地名ですね。七つのしよう乳洞があるという意味なのか, 七つの釜=ドリーネが7つあるという意味なのか!しらべてみてくたさい。
|
七釜しょう乳洞と反対側の間瀬層
 石灰ソウ類の化石を大量にふくんだ砂岩で,全体としては、西側にかたむき層理にそって溶食されています。 石灰ソウ類の化石を大量にふくんだ砂岩で,全体としては、西側にかたむき層理にそって溶食されています。石灰ソウ類の化石
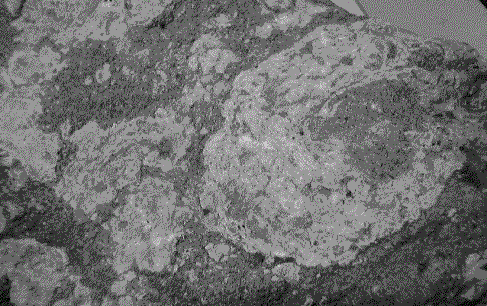 |
||
|
⑪大島町日切
干潮時のここでは、うすい砂岩と泥岩が交互に重なっている様子(互層)が見られます。西彼杵層群の最上部の日切層と呼ばれる地層で、砂岩と暗灰色の泥岩が多く、その間にギョウ灰岩をはさみます。キリガイダマシやフミガイなどの貝化石が見つかります。
砂岩泥岩の互層には、浸食を受けて波で削られた部分と、固く残っている部分と見られる。化石はどちらに残るのでしょうか。
|
 |
|
⑫大瀬戸町雪浦
雪の浦では滑石を使って、石鍋を製作していた跡がある(ホゲット)。下の図のようにじゃ紋岩と変成岩の間にできる滑石を利用していた。このような規則性があるので、探したい岩石は順に見ていくと見つかりやすいのです。
|
じゃもん岩と西彼杵変成岩類の接触変成帯にみられる規則性。牟田邦彦氏(1954)による。
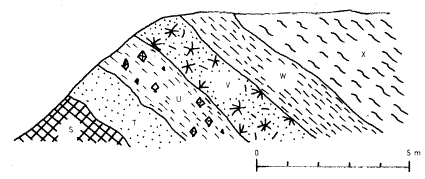 S じゃもん岩 T かっ石化帯
∪ 磁鉄鉱・緑でい 石化帯
∨ 緑でい石・そう 長石・絹雲母・ アクチノ閃石・ 透角せん石岩
W 絹雲母帯
X そう長石・石英・陽起石・緑でい石・絹雲母片岩
|
|||||||||||||||||||
|
外海町神浦
神浦を過ぎ、越首・赤首海岸では、呼子ノ瀬戸-多以良-外海断層となって、連続した大断層の影響が見られる。海岸が単調なこともそのためである。
池島
池島の頂上は玄武岩でできていて,平らな地形になっています。玄武岩マグマの粘りけは小さいため,流れやすくなだらかな地形をつくります。火山活動当時は,この付近一帯に広い玄武岩の溶岩台地が広がっていましたが,侵食され,その一部が池島に残ったものです。
⑬外海町黒崎
城の山は、変成岩を貫いて玄武岩が地下からでてきたのである。
角力(すもう)灘に点在する大角力・小角力は,玄武岩でできていて,塔状に突き出た形になっています。また,母小島や池島の上部にも,下部の西彼杵層群と呼ばれるたい積岩をおおって,玄武岩の溶岩が見られます。
|
||||||||||||||||||||
|
⑭長崎市樫山
仏崎より、樫山を望む。
波の浸食によって切り立った崖になっている。この崖は、玄武岩のスコリアでできた火山の断面である。
崖には、溶岩の層や角礫岩層がはっきり見える。落下物があるので離れた位置で観察しておこう。
|
||||||||||||||||||||
|
第1表 西樫山付近の火山層序表
西樫山へ向かって、第1表を下へ見ていくことになる。
|
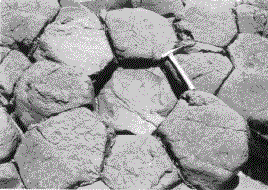 |
玄武岩の柱状節理
ここの玄武岩柱状節理は、きれいな6角形で、溶岩が冷えて固まるときできたものである。
また、周辺部の玄武岩には、ちがった種類の岩石を含んでいる。それは、この玄武岩が地上に上がってくる際、地下の深いところにある岩石を運んできたものである。
そのような岩石を捕獲岩という。
玄武岩を割って、斑晶を確かめてみよう。
|
||
| 赤土のような、スコリアがたい積しているところがある。この中には、火山弾、火山礫などが見られる。中にある白い固まりは、割ってみるとアラレ石の放射状結晶である。 | |||
 |
海岸のれきに、変成岩が増えてくると、そこは西彼杵変成岩地帯に入る。この辺から⑫で紹介した、変成岩の規則性が見られる。目的の鉱物を探してみよう。
代表的な鉱物として、
・黒く金属光沢を持つ、正八面体の磁鉄鉱(磁石で吸い付けると集めやすい)
・白~ベージュ~灰色~黄緑で爪で傷が付く滑石、こすると白い粉がでる。
・緑色の放射状の結晶で、刺さりそうな感じがするアクチノ閃石。
・うすくはげる感じで、魚のうろこのような鮮やかな緑のクロム雲母。
・緑色片岩中に、白色の四角い粒は、曹長石。
・透明感のある白は、石英。
・くすんだ黄緑の細長い結晶は、緑レン石。
・雲母のような緑色の結晶は、緑泥石
とにかく多くの鉱物があります。座り込んでじっくり探しましょう!
|
|
|
|
|