
 |
褶曲した緑色片岩 (千々海岸) | ||
| 1.地質図 | |||
|
|
|||
西彼杵半島・長崎半島には古い時代の変成岩類が分布し,これに先第三紀の深成岩類が貫入している。これらをおおって長崎南部および北部〜東部には,古第三紀〜白亜紀のたい積物が分布している。新第三紀になって流紋岩類・玄武岩類・安山岩類などの活動があったが,これらの山体は浸食によってほとんど消失してしまい,山稜は標高300−500m前後のなどらかな隆起準平原を形成している。おおむね壮年期の地形をしめし,平地に乏しくV字谷やおぼれ谷が発達する。長崎半島北部は,古生代の長崎変成岩類が,新生代の長崎火山岩類におおわれる境界付近にあたる。
|
|||
|
①茂木植物化石
長崎火山は火山活動の初期に火山灰や軽石などを多量に放出した。この時期には長崎火山周縁の各地に小さな淡水湖が形成され、この中に植物の葉・幹・根などが流れてきてたい積した。茂木植物化石層はこうして形成された淡水性の化石湖の1つで,長崎火山周縁には喜々津植物化石層をはじめこれに類似の化石湖が数多く分布する。
茂木植物化石群は,1879年10月長崎に寄港したスエーデンの科学者A.H.Nordenskioldが白岩海岸から採集して本国に持ち帰ったものを,古植物学者のA.G.Nathorst(ナトホルスト)が鑑定して約50種を報告して以来有名になり,その後 R.Florin(1920年)や矢部長克・遠藤誠道(1930年)らによって再検討され約74種が報告されている。
茂木植物化石層は約10mの厚さをもつが,化石種の縦の分布は特徴的である。まずFagus ferruginea(ブナ類)全層にわたって多産する。最下部から中部にかけてMetasequoia
sp.(メタセコイア)Liquidambar formosana(フウ)・Zelcowa keaki(ケヤキ)などが多く,中部以上では,上記のものがなくなり最上部にPhyllites
bambsoides(タケの類)が多くなっている。茂木植物化石層は植物化石のみを産し.動物化石はまだ発見されていない。近年ここの化石植物群と類似のものが各地で報告されている。
|
 |
||
 |
*ここで地層がどのようにできたかを、れきや砂の形や堆積の仕方で推測してみよう。
崖の地層をスケッチしよう。
↓
↓
推測しよう
基本 1、れきの粒が、とがっているか丸いか。
→丸いのは、水中を流された。
2、粒の大きさは、下ほど大きい。粒がそろっている。
→水中で漂っている小さな粒は、ゆっくり堆積した。大きい粒は、早く堆積した。
3、粒の大きさが、混ざっている。
→一気に堆積した。たとえば、土石流、火砕流。
4、粒が引き伸ばされていないか。
→高温の状態で堆積した。
|
||
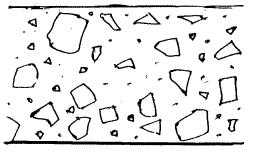 |
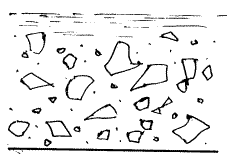 |
||
| 例 池などの静かな堆積環境であった | 火砕流が陸地に堆積した(炭化した木) | 火砕流が水中に堆積した | |
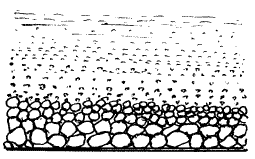 |
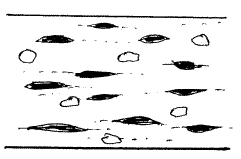 |
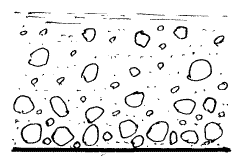 |
|
| 火砕流が高温のまま堆積した | 一気に土石流が流れ込んだ |
黄鉄鉱〜武石を含む緑色片岩 C地点
褶曲した黒色片岩
断層:右:緑色片岩 左:黒色片岩 以外宿より綱掛岩 野母変はんれい岩複合岩体
⑦小ヶ倉 褶曲・不整合
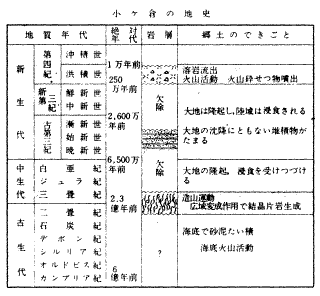 堆積岩は結晶片岩より後に堆積したのであるが、それぞれの生成年代は6千万年前と約2億年前である。現在上下に相接する2種の岩層の間には,実に1億余年の莫大な時間がはさまれている。2種の岩石は不整合に重なり合っているのである。
堆積岩は結晶片岩より後に堆積したのであるが、それぞれの生成年代は6千万年前と約2億年前である。現在上下に相接する2種の岩層の間には,実に1億余年の莫大な時間がはさまれている。2種の岩石は不整合に重なり合っているのである。

*化石の処理:今回の化石は壊れやすいので、木工ボンドを水で薄く溶き、ていねいに薄く塗ります。今日帰ったらすぐ実行してください。 |
jun.htmlへのリンク